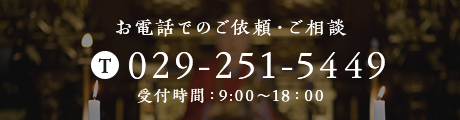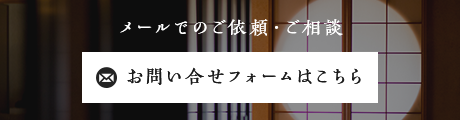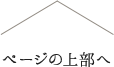カテゴリー: お役立ち情報
【今月の聖語】十界互具これを説く
2024年10月17日
【今月の聖語】十界互具これを説く
『如来滅後五五百歳始観心本尊抄』/文永10年(1273)52歳
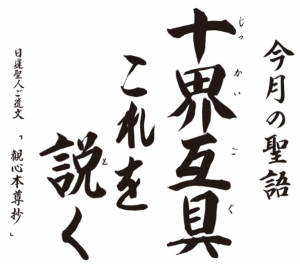
「優しさの心」
日蓮聖人が信仰された法華経には、「十界互具」(じっかいごぐ)という教えがあります。
十界とは人の状態・ありようを表したもので、地獄のような迷いの状態から、仏の悟りのような清らかな状態を十の境界で示したものです。
そしてこれらの十の境界は別々に存在するわけではなく、常に折り重なっており、善と悪を行ったり来たりしてしまうと説かれています。
たとえば完全な悪人がいないように、完全な善人であることが難しいように、私たちは自然と他人を気遣うこころを出すこともあれば、時には利己的な考えに支配されそうになる瞬間があります。
しかし、人もまた折り重なるようにこの社会で関係しあって生活をしています。優しい心が他人の善を呼び起こすこともあるでしょう。自分自身の独善的な感情が伝播するように他人の悪感情を引き出してしまうかもしれません。
争いや不和の絶えない私たちの世界の平和は、一人ひとりの「優しさの心」が響き渡ることで現れてくるのではないでしょうか。
◆本行寺のご紹介◆
本行寺は仏教の中で日蓮宗という宗派のお寺で、インドで仏教を説いたお釈迦様と日本で仏教を弘めた日蓮聖人を宗祖として信仰しています。日蓮聖人は鎌倉時代の僧侶で、乱世の時代に仏の教えによって人々を救おうとされ、現代でもその説かれた教えが受け継がれています。
宗教といえば、仏教のほかにも世界にはいろいろなものがあります。私たちが住む日本でも神道やキリスト教などをはじめ多くの宗教が信じられ、その中に仏教も含まれています。
神道は日本の神様についての教え、キリスト教はイエス・キリストが説いた教えです。では仏教はというと、他の宗教と比べ仏教の特徴としては、仏教は「仏が説いた教え」であり「仏になるための教え」でもあるとよく言われています。
ここでいう仏とは私たちが思い描く「神様」とは少し違う存在です。仏教では私たちの住む世界は苦しみの多い世界だと説かれています。仏とは真理を悟り煩悩や欲望から解きはなたれることで、その苦しみから離れた者のことであると説かれています。
ですので、仏教には仏になる方法=苦しみや悩みから救われる方法が説かれている宗教だとも言えるのです。
その他のお役立ち情報
- 2024年10月17日【今月の聖語】十界互具これを説く
- 2024年9月6日定期清掃完了のお知らせ
- 2024年6月6日2024年 お盆(盂蘭盆会)について
- 2024年6月5日定期清掃完了のお知らせ
- 2024年3月13日定期清掃完了のお知らせ
- 2023年12月22日年末年始の行事のご案内
- 2023年12月7日12月22日(金) 星祭り開催いたします
- 2023年10月23日安産祈願はいつやるべき?安産祈願の参拝時期について
- 2023年8月24日今月の聖語「南無と申す字は敬う心なり」
- 2023年6月19日にいぼんおせがき供養のお知らせ
- 2022年7月11日お盆(盂蘭盆会)について
- 2022年2月3日入り口改修・駐車場整備のための工事
- 2021年12月23日【除夜の鐘、初詣など】年末年始の行事のご紹介
- 2021年10月20日今月の聖語「仏と申すは正直を本(もと)とす」
- 2021年9月9日当山のご紹介
- 2020年4月20日現役住職が教えるお寺で行う会社の商売繁盛祈願のポイント
- 2019年12月2日厄除けを受ける方に読んでほしい4つの話
 お役立ち情報
お役立ち情報
定期清掃完了のお知らせ
2024年9月6日
日頃より本行寺にご参拝いただきありがとうございます。
この度は、下記日程にて定例の墓地清掃を実施致しました。
・9月3~4日…除草作業
当山では、ご参拝の皆様がご縁のある御霊位様のお墓に心安らかにお参りができますよう、定期的に清掃に入って頂いております。
行事や普段の墓参によりご霊位様への供養によって縁を深め、共に心安らかにお過ごしになれる場所となることを心掛け、これからも勤めて参ります。
その他のお役立ち情報
- 2024年10月17日【今月の聖語】十界互具これを説く
- 2024年9月6日定期清掃完了のお知らせ
- 2024年6月6日2024年 お盆(盂蘭盆会)について
- 2024年6月5日定期清掃完了のお知らせ
- 2024年3月13日定期清掃完了のお知らせ
- 2023年12月22日年末年始の行事のご案内
- 2023年12月7日12月22日(金) 星祭り開催いたします
- 2023年10月23日安産祈願はいつやるべき?安産祈願の参拝時期について
- 2023年8月24日今月の聖語「南無と申す字は敬う心なり」
- 2023年6月19日にいぼんおせがき供養のお知らせ
- 2022年7月11日お盆(盂蘭盆会)について
- 2022年2月3日入り口改修・駐車場整備のための工事
- 2021年12月23日【除夜の鐘、初詣など】年末年始の行事のご紹介
- 2021年10月20日今月の聖語「仏と申すは正直を本(もと)とす」
- 2021年9月9日当山のご紹介
- 2020年4月20日現役住職が教えるお寺で行う会社の商売繁盛祈願のポイント
- 2019年12月2日厄除けを受ける方に読んでほしい4つの話
 お役立ち情報
お役立ち情報
2024年 お盆(盂蘭盆会)について
2024年6月6日

日頃より当山にご参拝いただき誠にありがとうございます。
本行寺では、下記日程において2024年度お盆の法要を法要を執り行います。。
■7月13日…新盆にあたる当家向け
■7月16日(火)…一般参拝者向け
■8月13日(火)…一般参拝者向け
※お電話にて塔婆供養の受付も可能です。
その他のお役立ち情報
- 2024年10月17日【今月の聖語】十界互具これを説く
- 2024年9月6日定期清掃完了のお知らせ
- 2024年6月6日2024年 お盆(盂蘭盆会)について
- 2024年6月5日定期清掃完了のお知らせ
- 2024年3月13日定期清掃完了のお知らせ
- 2023年12月22日年末年始の行事のご案内
- 2023年12月7日12月22日(金) 星祭り開催いたします
- 2023年10月23日安産祈願はいつやるべき?安産祈願の参拝時期について
- 2023年8月24日今月の聖語「南無と申す字は敬う心なり」
- 2023年6月19日にいぼんおせがき供養のお知らせ
- 2022年7月11日お盆(盂蘭盆会)について
- 2022年2月3日入り口改修・駐車場整備のための工事
- 2021年12月23日【除夜の鐘、初詣など】年末年始の行事のご紹介
- 2021年10月20日今月の聖語「仏と申すは正直を本(もと)とす」
- 2021年9月9日当山のご紹介
- 2020年4月20日現役住職が教えるお寺で行う会社の商売繁盛祈願のポイント
- 2019年12月2日厄除けを受ける方に読んでほしい4つの話
 お役立ち情報
お役立ち情報
定期清掃完了のお知らせ
2024年6月5日
日頃より本行寺にご参拝いただきありがとうございます。
この度は、下記日程にて定例の墓地清掃を実施致しました。
・5月25~26日…除草作業
・6月4~5日…参道の整備
当山では、ご参拝の皆様がご縁のある御霊位様のお墓に心安らかにお参りができますよう、定期的に清掃に入って頂いております。
行事や普段の墓参によりご霊位様への供養によって縁を深め、共に心安らかにお過ごしになれる場所となることを心掛け、これからも勤めて参ります。
その他のお役立ち情報
- 2024年10月17日【今月の聖語】十界互具これを説く
- 2024年9月6日定期清掃完了のお知らせ
- 2024年6月6日2024年 お盆(盂蘭盆会)について
- 2024年6月5日定期清掃完了のお知らせ
- 2024年3月13日定期清掃完了のお知らせ
- 2023年12月22日年末年始の行事のご案内
- 2023年12月7日12月22日(金) 星祭り開催いたします
- 2023年10月23日安産祈願はいつやるべき?安産祈願の参拝時期について
- 2023年8月24日今月の聖語「南無と申す字は敬う心なり」
- 2023年6月19日にいぼんおせがき供養のお知らせ
- 2022年7月11日お盆(盂蘭盆会)について
- 2022年2月3日入り口改修・駐車場整備のための工事
- 2021年12月23日【除夜の鐘、初詣など】年末年始の行事のご紹介
- 2021年10月20日今月の聖語「仏と申すは正直を本(もと)とす」
- 2021年9月9日当山のご紹介
- 2020年4月20日現役住職が教えるお寺で行う会社の商売繁盛祈願のポイント
- 2019年12月2日厄除けを受ける方に読んでほしい4つの話
 お役立ち情報
お役立ち情報
定期清掃完了のお知らせ
2024年3月13日
日頃より本行寺にご参拝いただきありがとうございます。
この度は、3月4日に定例の墓地清掃を実施致しました。
当山では、ご参拝の皆様がご縁のある御霊位様のお墓に心安らかにお参りができますよう、定期的に清掃に入って頂いております。
行事や普段の墓参によりご霊位様への供養によって縁を深め、共に心安らかにお過ごしになれる場所となることを心掛け、これからも勤めて参ります。
その他のお役立ち情報
- 2024年10月17日【今月の聖語】十界互具これを説く
- 2024年9月6日定期清掃完了のお知らせ
- 2024年6月6日2024年 お盆(盂蘭盆会)について
- 2024年6月5日定期清掃完了のお知らせ
- 2024年3月13日定期清掃完了のお知らせ
- 2023年12月22日年末年始の行事のご案内
- 2023年12月7日12月22日(金) 星祭り開催いたします
- 2023年10月23日安産祈願はいつやるべき?安産祈願の参拝時期について
- 2023年8月24日今月の聖語「南無と申す字は敬う心なり」
- 2023年6月19日にいぼんおせがき供養のお知らせ
- 2022年7月11日お盆(盂蘭盆会)について
- 2022年2月3日入り口改修・駐車場整備のための工事
- 2021年12月23日【除夜の鐘、初詣など】年末年始の行事のご紹介
- 2021年10月20日今月の聖語「仏と申すは正直を本(もと)とす」
- 2021年9月9日当山のご紹介
- 2020年4月20日現役住職が教えるお寺で行う会社の商売繁盛祈願のポイント
- 2019年12月2日厄除けを受ける方に読んでほしい4つの話
 お役立ち情報
お役立ち情報
年末年始の行事のご案内
2023年12月22日
2023年も残るところあと少し。これまでの一年を振り返り、新しい年がより素晴らしいものになるように祈願することは、新しい一歩を歩んでいくという意味でも年末年始の行事は一つ節目になることでしょう。当山でも大晦日には、皆さんがより良く新年を迎えられるような仏事を執り行っています。

◆除夜の鐘 (11時半前ごろ~):ご自由にご参加ください
除夜の鐘とは、心穏やかに信念を迎えようという意味を込めて”除日”と呼ばれる大晦日の夜から行う行事です。古来ではお寺にある鐘はもともと除夜の鐘に限らず日々の日課として百八回打ち鳴らすのが正式な作法でした。これは人間がもつ煩悩の数である「百八」をひとつずつ打ち消す意味がこめられ、現代では特に除夜の鐘の際煩悩を払うために百八回ついていきます。
本行寺でも、地域の方々や檀家様、その他ご参拝者様に向けて大晦日の除夜の鐘を開放しております。当山では夜の11時半ごろに、本堂前の鐘にてご希望者様に鐘をついていただき、新年を迎える準備をしていただいております。

◆住職による読経
除夜の鐘とはじまりと同じころから、本堂では住職による読経が始まります。この読経では、本年を無事に過ごすことができたことの感謝と、新年がより良い年であるようにと祈願する意味が込められており、除夜の鐘と並行して行われます。本堂内で行われている読経中はどなたでもお参りができますので、お気軽にお参りください。

◆初詣 (元旦より)
初詣は、これまでの一年間を無事に過ごせたことを神仏に感謝し、新しい一年も健全に過ごせるようにご挨拶に行くことです。初詣では、檀家になっている菩提寺や近所の氏神様が祀られている神社さんへのご参拝が基本的なご参拝先になりますが、現代では縁のある寺社仏閣への複数箇所へ初詣に行くこともよろしいでしょう。
大切なのは新年祈願のご挨拶に行くというお気持ちですので、お気軽にご参拝ください。
ここまで「除夜の鐘」「読経」「初詣」と大晦日から年始にかけての行事についてご紹介いたしました。
年末年始の行事は、これまでの一年を振り返り、新たな一年を迎えるために行われる大切な行事です。
本行寺は、茨城県水戸市に根付く400年以上の歴史があるお寺です。ご参拝からご供養、ご祈祷など年間を通していつでも行っており、このような行事・仏事を通して皆様の心の支えになれるよう心がけています。檀家様、地域の方々、その他ご参拝者様による年末年始の仏事参加を心よりお待ちしております。
その他のお役立ち情報
- 2024年10月17日【今月の聖語】十界互具これを説く
- 2024年9月6日定期清掃完了のお知らせ
- 2024年6月6日2024年 お盆(盂蘭盆会)について
- 2024年6月5日定期清掃完了のお知らせ
- 2024年3月13日定期清掃完了のお知らせ
- 2023年12月22日年末年始の行事のご案内
- 2023年12月7日12月22日(金) 星祭り開催いたします
- 2023年10月23日安産祈願はいつやるべき?安産祈願の参拝時期について
- 2023年8月24日今月の聖語「南無と申す字は敬う心なり」
- 2023年6月19日にいぼんおせがき供養のお知らせ
- 2022年7月11日お盆(盂蘭盆会)について
- 2022年2月3日入り口改修・駐車場整備のための工事
- 2021年12月23日【除夜の鐘、初詣など】年末年始の行事のご紹介
- 2021年10月20日今月の聖語「仏と申すは正直を本(もと)とす」
- 2021年9月9日当山のご紹介
- 2020年4月20日現役住職が教えるお寺で行う会社の商売繁盛祈願のポイント
- 2019年12月2日厄除けを受ける方に読んでほしい4つの話